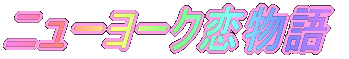
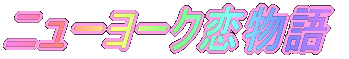


一週間は夢ように過ぎていった。
大沢と今日子は毎朝肩を並べて東京のオフィスへ向かった。
駅までの10分の道のりを短く感じるのは
大沢の話がとても面白いからだった。
毎朝大沢は今日子をよく笑わせてくれた。
帰りはいつも渋谷で待ち合わせをして必ず一緒に帰った。
時にはたくさんの食材を買って帰り、部屋で食事をした。
こんな季節に鍋は可笑しいけれど
ニューヨークでは鍋などすることは無いと言って大沢は喜んだ。
毎日が新鮮で夢のようだった。
月曜日には大沢はニューヨークへ帰ってしまう。
けれど今は別れのことなど考えないで、精いっぱい楽しく過ごしたかった。
日曜日、大沢は今日子に素敵な一日をプレゼントしてくれた。
久しぶりに二人でドライブだ。
今日子は嬉しくて朝からバスケットいっぱいのランチを作った。
昨夜心配して吊るしたてるてる坊主は忠実に約束を果たしてくれた。
今日は雲ひとつない青空だ。
大沢と今日子は湘南の海へ出かけた。
大沢の運転するレジェンドは風を切って走った。
海開きまでまだ1ヶ月以上ある。
今頃の海はとても静かで、サーフボードを持った若者のグループがいた。
若者はサーフィンを始めたり、ビーチで戯れたり
その若さに二人は少し眩しさを感じていた。
「若いっていいよね」 今日子が言うと
「僕たちも彼等に負けないくらい若いよ」と大沢は言った。
今日子は若くないから、色々に考えて・・・
色々考えるから踏み切れないことがたくさんあって、仕事を辞められない。今日子にとって大沢も仕事も大切で、天秤に掛けられないでいた。
ビーチに大きなシートを敷いて
今日子はバスケットからランチを出した。
サンドイッチにホットドック・・・・。天むすびも作った。
フライドチキンに卵焼きにウインナーソーセージ。
バスケットの中はすべて大沢の好物のものばかりだった。
「僕、このウインナー大好き」
そう言って箸で摘んだのは真っ赤なタコウインナー。
「僕このりんご大好き」
そう言って手づかみしたのはウサギの耳を形どったりんご。
子供が喜ぶようなことをすると、決まってはしゃいで喜ぶ大沢を
今日子はとても可愛らしいと思った。
二人は昔から湘南の海を見ながら過ごすのが好きだった。
寄せては返す波はまるでレモンソーダーの泡のように消えた。
潮の香りを体中で感じると、日常の疲れをかき消した。
潮風は今日子の髪を乱した。
今日子は右手で髪を押さえながら、大沢に語りかける。
「ねえ・・・私 仕事辞めようかしら?」
大沢は今日子の揺れる気持ちが手に取るようにわかっていた。
大沢は「仕事を辞めろ」と言うことが今日子の幸せなのかと考えた。
今日子にとって子供の頃からの夢が叶った職業だった。
今、一人の男のためにその夢を捨てさせていいのかと。
大沢は自分に自信はあったが、
一方ではとても裏腹な自信喪失の自分がいた。
「ゆっくり考えて結論を出しなさい。僕はいつまでも待っている」
大沢はそういうのがやっとだった。
どれくらい湘南のビーチでいただろう。
パラソルの下で寝転んで二人は他愛もないおしゃべりをした。
一緒にいると安堵の気持ちでいっぱいになった。
夕陽はゆっくりゆっくり西に傾き始めた。
大沢の車は湘南から「みなとみらい」へと向かった。
「お家に帰らないの?」 今日子がそう言うと
「ランドマークタワーへ行こう」と大沢は言った。
今日子は首をかしげながら大沢の指示に従った。
ランドマークタワーではよく食事やショッピングをした。
日曜日にはここで待ち合わせてみなとみらいでデートした。
二人にとって楽しい場所でもあった。
ランドマークタワーの52階からは高層ホテルの客室だった。
大沢は今日子を残してフロントに行った。
今日子にはその意味がわからなかった。
しばらくして今日子のところに戻ると大沢は言った。
「今夜はこのホテルでお泊りだ」
今日子は驚いて
「嘘でしょう? からかわないで」 と言った。
「ホラ!僕たちのルームキーだよ」
今日子は言葉を失った。
大沢がランドマークタワーにあるホテルを予約してくれていた。
摩天楼のビルから夜景を見ながら最後の夜を過ごそうと言うのだ。
ベルボーイがフロントから部屋に案内してくれた。
部屋はベイサイド側の64階のスイートルームだった。
今日子はまだ信じられなかった。
「嬉しいわ。私、こんなに幸せでいいのかしら?」
もっと嬉しい気持ちを言葉にして大沢に伝えたいのに
胸がいっぱいで言葉が出てこなかった。
一週間は短かった。
今夜は二人で過ごす最後の夜だ。
こんな素敵な部屋を二人のためにと思うと
今日子は大沢が切ないくらい愛しかった。
「今夜みなとみらいでもうひとつ行っておきたいところがある」
大沢は今日子に言った。
「明日ニューヨークに発つ前に、赤レンガ倉庫に行っておきたい」
ミレニアムの年にあるイベントがあって
大沢と今日子は赤レンガ倉庫で初めて出会った。
どちらも友人を介しての出会いだったけれど
二人は初めて会った時からお互い不思議な魅力を感じていた。
大沢は今日子の聡明さに憧れていた。
女にしておくには惜しいと思うことがあった。
けれどいつも謙虚で女らしくて家庭的であった。
今日子もまた大沢の知識の豊富さに憧れていた。
何を話しても大沢は知らないことがなかった。
けれどいつもそれを自慢するでもなく優しくて穏やかだった。
そんな二人が付き合い始めるにはそれほど時間が掛からなかった。
みなとみらいの「赤レンガ倉庫」は二人の出会いの場所であった。
そこに立つと、その日の大沢と今日子が戻って来た。
真っ直ぐな長い黒髪。
パープルのスカートに黒のセーター。
バーキンを持っていたけれど、少しも嫌味ではなかった。
きっと物腰の柔らかさがそうさせたのだと思う。
「初対面の時、あなたはここで私のバーキンばかり見ていたわ」
「だってこの年でバーキンだなんて
これはどこかの叔父様のプレゼントかと思ったよ」
「失礼ね。趣味はバックよ。そのために働いているんだから」
「でも今日子がバーキンを持つと嫌味じゃないんだな。
今日子はバーキンがよく似合う女だよ
今日子のキャリアとステータスが君を浮き上がらせない」
二人は思い出話を始めた。
他愛もないやり取りを月が見て笑っていたかもしれない。
そんな幸せな二人にも時間は止まることなく流れた。
砂時計の砂の落ちる音が耳元でする。
切なくてやりきれない音だ。
「今日子、帰ろう。ホテルの部屋に戻ろう」
そう言って大沢は今日子の手を繋いだ。
みなとみらいでの夜を美しい思い出にしたいと思いながら
二人はランドマークのホテルに向かって歩き出した。
